こんにちは!育休は取らなかったけど、育児はずっとしていた兼業主夫のリン☆だあく(@rindark)です〜!
ネットニュースを見ていたらこんな記事見かけました。まさに、わたしの言っていた事だったので、わたしも便乗して記事を書いてみたいと思います。
“育休はまったく“休暇”じゃなかった。つるの剛士がR25世代に伝えたい「男と仕事と家庭」“

【もくじ】
つるの剛士さんが実感した、育児で女性と男性では”OS”のバージョン違いが・・・、仕事だけではダメ

女性は、子供を産むと変わります。これは間違いなくです。やっぱり体で繋がっていたこともそうだし、おっぱいをあげることもその一つの要因だとわたしは思います。
しかも、女性は現在は一般的に子育てするものと認識されていることが多いので情報量も違います。
そんな理由から、女性は子供を産むと結婚して奥さんという立場から、「ママ」にOSがバージョンアップするとつるの剛士さんがおっしゃっています。うちも同じようなことが起こりました。
わたしも最初から主夫だったわけではなく、モーレツに働く会社員でした。
また、残業の規制とかが厳しくなかった時代なので、36時間連続勤務をしたり、1週間続けて、夜中の12時を過ぎるまで仕事をしたりしていました。
そんな働きかただと、全然家庭のことなんか見れるわけもなく、体調を崩して会社を辞めるまではそんな感じでした。
こんな風にスタート地点が全然違う男女ですが、それでも男性も始めてしまえば前に進みます。最初は慣れない家事、育児で辛いかもしれないけれど、慣れて行けば、家事、育児”OS”もバージョンアップします。
会社を辞めて再就職して

仕事を辞めてからは、1番目の子供である娘との時間が取れるようになり、妻が今度は仕事が忙しい会社に転職しました。なので、娘が保育園に入る頃には、わたしが毎日保育園の送り迎えをするようになりました。
その頃には、わたしも再就職をしていたので、仕事もあったのですが、娘をみるために残業のない職場を探し、そこに就職先を決めていました。
わたしのやり方は極端なので、あんまりオススメはできません。
給料が減る可能性もありますし、うまく再就職ができない場合もあるからです。なるべくなら、今の会社に残りつつ、働き方を変えていくのが理想です。
育児の環境で自分の”OS”もバージョンアップ
娘が生まれて少ししてから、妻が夜勤のある仕事に変わったので、わたしもそれに対応して家庭のことをさらにやることになりました。最初は家事は、ご飯作りからでした。
娘のことは、ミルクの調合と、オムツ交換からでしたね。
それ以前からしていたお風呂入れも、以前は妻と協力して入れていたのですが、妻が夜勤でいない時には、一人でお風呂入れをしていましたねぇ。最初はなかなか難しくて大変でした。自分の着替えなどは二の次でしたね。
それでも慣れてくれば、ささっと娘を拭いて、服を着せて自分の着替えをして、湯上りの湯冷ましを娘にあげたりしていましたよ。
そんな生活をつづけていたら、今度は息子も生まれて、4歳の娘と生まれた息子の二人を一人で面倒みるということもこなしていました。妻が休みだったりした時には心からホッとしたのを覚えています。
そうやってだんだんとバージョンアップしていって、妻が単身赴任をする事になる頃には、ワンオペで家事、育児、仕事をこなせるようになっていました。

つるの剛士さん曰く、育児休業は男の「家庭訓練」の期間

育児をするのに、わたしのように転職して対応というのは珍しいかもしれません。通常ならば、育児休業を取って、「家庭訓練」、育児に入るのが近道だと思います。
本当に訓練という言葉がふさわしいぐらい育児は意外と大変です。わたしも経験しましたが、仕事の方が何百倍も楽ちんです。時間も、体もトイレに行くのも自分の自由にならない世界ですから。
今でも覚えている辛いことは、娘が夜寝ない子で、寝かしつけにかなり苦労したことですね。おんぶして、一階と二階を何十往復したり、車のベビーシートに乗せて夜中のドライブをしたりしていました。
不思議とドライブ中は眠るのですが、寝たなと思って、布団に下ろすとパチっと目を覚まし、二度目のドライブに出かけたりもしていました。娘が寝る頃は夜中の3時過ぎなんてざらでしたね。
土日も妻は仕事の事が多くて、わたしは、家にずっといるのが耐えられなかったので、近くのイオンによく子供達と出かけていました。
なぜイオンかというと、当時から、男性トイレ赤ちゃんベットがあったり、ベビー用品売り場には、赤ちゃん休憩室があったりして、オムツやミルクがやりやすかったと言うのもありますし、自分の気分転換にいろんな商品を見るのも楽しかったのもあります。
帰り際に夕飯の買い物とかをして、帰ると言うのがあの頃の土日の過ごし方でしたね。
そうやって何もできなかったパパでも、日々訓練を重ねていくと、スキルが上がって子供達との絆や妻との会話の糸口にもなり、そこには仕事だけでは見えなかった世界が広がっていましたね。
それは、辛いだけではなく、自分の生活力というのもかなりバージョンアップしたし、わたしもこうして「家庭訓練」ができたことはすごくいい経験だったと今では思えます。
育児休業でわかる、つるの剛士さんも体感、喋りたい欲求。家庭も大変なんです。

小さい赤ちゃんがいると1日誰とも喋らずに終わることがほとんどです。もう誰でもいいから人間と喋りたいという欲求がすごく湧いてくるんですよねぇ。
赤ちゃんはまだ人間語が喋れないので、会話という会話にはならないし、わたしの場合は自分の両親が頼れなかったのと、妻の両親は仕事をしていたので、常にこういう時はワンオペでやっていたので、夕暮れになる頃にはかなりのフラストレーションが溜まっていました。
そういう経験をしているからか、子供達が保育園に入る頃にはよそのママ達と会話が合うこと合うこと。喋ることが尽きないぐらいでしたよ。
つるの剛士さんもおっしゃっていますが、保育園のお迎えのときにはおしゃべりが苦手なわたしでさえも、ママ友たちとお話しするのが楽しみになるぐらいでした。
夜勤じゃない妻が夜に帰ってくると、ホッとして夫婦の会話がすごくありがたいと思える日々でした。
育児が育てる夫婦の絆

パパたちも育児に積極的に参加することによって、妻と夫の間には強い絆が生まれます。
子供を育てるのは本当に大変で、きちんとお互いをサポートしあえれば、夫婦の間には一緒に困難を乗り越えた戦友にも似た感情も生まれて、今まで以上の関係が築けますよ。
その絆は、たとえ子供達が大きくなっても続くし、将来の夫婦だけの時間も良好に過ごすことができるようになるとわたしは確信しています。
やっぱり、育児の大事をほったらかしにしていた夫というのは、将来邪魔扱いされやすいんじゃないかなぁって予想します。
育児を二人できちんとできれば、妻もこの人は困難を分かち合ってくれる人と認識してくれるはずです。
まとめ
姉妹サイトの別の記事でも書いていますが、育児をする事は大変な事だけではありません。ぜひぜひ、男性にもきちんと育児を体験してもらいたいと切にわたしは願っています。
家事、育児を経験した後に見える世界は、仕事だけでは得られない広い世界です。

それでは、またね。

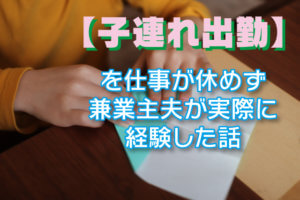





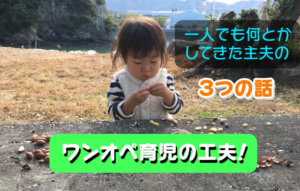
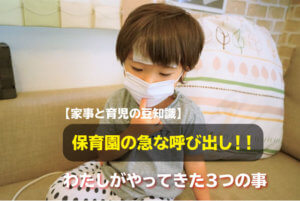
コメント